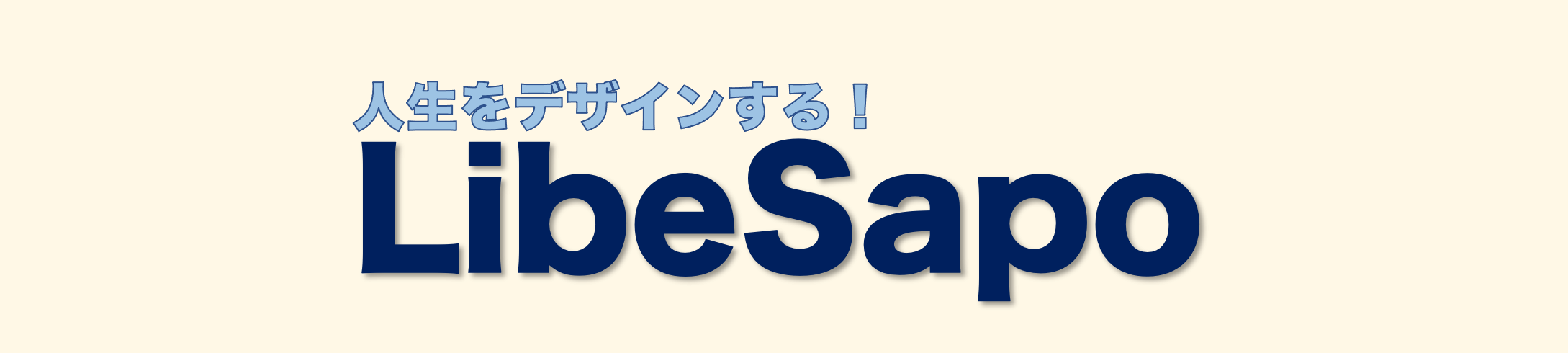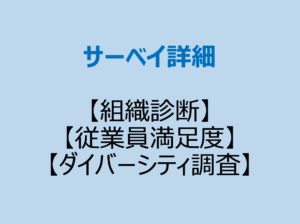【パワハラ防止】上司が部下に言ってはいけない言葉ベスト5!
この6月からパワハラ防止法が施行されたことは、ご存知でしょうか?罰則規定はないものの、上司の不用意な言動が、SNSでの拡散やテレビのワイドショーのネタになり、企業イメージを損ねることになる可能性があります。
判例関連のセミナーやゼミナールを受講したことがある方はご存知だと思いますが、裁判沙汰となり、判例に◯◯(社名)事件として名を残すこともなるのも嫌ですよね。
それはともかく、本来ハラスメントを防止する目的は、組織のパフォーマンス低下の抑制、社員の健康被害(メンタル不調)の低減、離職者の防止などです。ハラスメントによる会社の損害は目に見えないが重大であると言えるのです。
基本的にハラスメントは、上司の油断やおごりなどで発生します。特に、昭和体育会系の人間にとっては、自分たちにとっては、ごく当たり前だったこともハラスメントと言われてしまう時代です。
上司は時代に合わせた、部下への動機付け、育成、プライベートへの配慮をしなければいけません。残念ながら「オレの時代は」は通用しない世の中になってしまったのです。
そんな中、自分が発した言葉を客観的に振り返ることで、そんなつもりではなかった・・・という事態を避けて、皆がイキイキ働ける環境作りを心がけていきましょう。それではいってみましょう!
第5位 上司が部下に言ってはいけない言葉 「評価に影響するぞ」
自分が評価者であることをチラつかせて、常に上下関係を意識させ服従させようとする言葉です。「おまえ、次の評価わかってんだろうな」とか「もうすぐ評価査定会議だぞ」など、暗に評価下げてもいいのかな、という脅しでしかありません。
職場の地位・優位性を利用した立派なパワハラと言えるのではないでしょうか。(パワーハラスメント3つの定義の一つ)
まあ上司としては、部下を簡単に服従させる便利な言葉ですが、このような言葉を使っていては、中長期的に見て部下からの尊敬や敬意は得られることはありません。
たいがい部下は、これは脅し文句だなと感覚的に知りつつ面倒臭いことにならないよう、愛想笑いを浮かべながら上司の言う通りに行動することでしょう。しかし、この上司の薄っぺらさは、はっきりと認知していなくても気づいているのです。
指示命令には動機付けが必要です。この、評価をチラつかせるケースは外的動機付けと言えます。外的動機付けは、緊急事態やスピードを要求される場面では効果的ですが長く続くことはありません。
部下も人間です。外的動機付けばかりされると、疲れてきて、いったい何のためにやっているのかなと考えるようになります。そして気づきます。「私のやりたいことは、こんなことじゃない、ここにいていいのかと」
人は、「やりがい」「成長」「環境」を定期的に棚卸して、現在地を確かめたいものです。そして、その延長線上にある5年後、10年後どうなるのかを考えた時、こんな上司のいる会社じゃダメだと認識します。
部下は心の中でこう叫ぶはずです。
「評価?勝手に下げれば。正しく部下の評価をできないおまえの価値も下がるぞ」
第4位 上司が部下に言ってはいけない言葉 「誰のおかげだと思っているんだ」
あらゆる場面で、部下に対してマウントを取るための言葉です。そもそも部下に尊敬されていれば必要のない言葉ですが、年功序列だか何だか知らないが、実力もないのに部下を持つ立場になってしまった悲しい人です。
何かにつけ部下から感謝の言葉を引き出すことによって、自分の存在価値を確かめずにはいられない◯◯の穴のちぃっちゃい人間とも言えます。
余程、自分に自信がないがないのか、いちいちこんな言葉で確認されると、部下としては本当に面倒くさいですね。こんなんで、部下からの信頼は得られないでしょう。
部下の出した成果が、本当に上司のおかげだとしても、そこは「よくやったな」と労うのが上司としての役目だと思うのです。上司としての器の大きさを示してほしいです。
時々、マネジャークラスの方と会話をすると「あいつはオレが育てた」とか「オレが引き揚げてやったんだ」とか部下のことを言う人がいますが、構造は一緒かもしれません。
人は環境によって成長したり、悪い方向に行ったり、病気になったりします。上司のやるべきことは、部下に成果を出せる環境であったり、成長できる環境を与えることに尽きます。
その環境の中で、部下は部下自身の力で成長するものです。その与えられた環境によって部下から感謝されることはあるが、成長自体は部下の成果以外の何者でもありません。
人を成長させると言う言葉は、とてもおこがましい言葉であります。人が成長できる環境を提供する、と言うことが、人を人として尊重した真の人間関係であると言いたい。
部下は心の中でこう叫びます。
「おまえのおかげだけは、絶対にないな。でもおまえを反面教師としたおかげかもな」
第3位 上司が部下に言ってはいけない言葉「何でこんなこともできないんだ」
何かミスをした時に叱責され言われる言葉です。「こんなの常識だろ」とか「何年やっているんだ」とかも同じ部類の言葉でしょう。
上司が怒る理由はいろいろあります。部下への期待値が大き過ぎた場合や上司自身に火の粉が飛んできた場合やただ単に怒りたい場合などが考えられます。
この言葉は、第4位の「誰のおかげだと思っているんだ」と一緒で疑問形です。「誰のおかげだと思っているんだ」に対しては「あなたです」と答えないとさらに怒られます。
しかし、同じ疑問形であっても「何でこんなこともできないんだ」と言う質問に対して「教わってませんから」などと、まともに答えるとさらに怒られます。
このようなことを言う上司に慣れた方だと正解は「申し訳ありません」以外の選択肢はないと承知していると思います。
翻訳すれば、「おまえミスしやがって、オレに迷惑かけたんだから謝れ!」という感じでしょうか。こんなこと言うのは、本当にちぃっちゃな人間です。
このまま言ってしまうとさすがに自分の器の大きさがバレてしまうので、「何でこんなこともできないんだ」という疑問形の言葉になるのでしょう。とても浅はかな考えです。
上司は、部下が仕事をする上での知識や技術を見極めて、不足しているならば追加教育をすることが重要な役目です。
何も把握せず起こったことに対して、ただ指摘や叱責をする上司は、真のリアクション上司と言えるでしょう。こんな上司の下についてしまったのは不幸だとしか言えません。
心の中でこう叫びましょう!
「おまえの部下だからできないんだよ。何でそんなこともわからないのか」
第2位 上司が部下に言ってはいけない言葉「やる気あるのか?」
この言葉を言われると本当にやる気がなくなります。とても曖昧で汎用性が高いため、上司があらゆる場面で好んで使うパワハラ言語の代表格です。
そもそも「やる気」とは何か?仕事上では「モチベーション」と言われることが多い。日本語に戻せば「動機」または「意欲」と言うことになる。
確かに、モチベーションが低い、意欲がない=やる気がないと言う考えは、あっているように思える。ただし、抽象的な概念なので、やっぱり曖昧です。
上司がやるべきことの1つは、部下に仕事の「やりがい」を持たせることです。それが動機付けとなりモチベーションが向上します。モチベーションが高い人は「やる気」のある人と言えます。
一般的に、ハキハキと声が大きかったり、動きが俊敏であると好印象を与えることができる。基本、元気ならばやる気があると思われるかもしれない。
しかし、本当の「やる気」とはしっかりと仕事に対しての動機付けがされており、「目標達成意欲」や「問題解決力」「思考力」が高水準で発揮されている状態のことを言います。
このことを実現するには、上司がリーダーシップを発揮しビジョンを示すことや説明責任を果たすことが必要です。
これをやらずに、「やる気あるのか?」の一言で終わらす上司は、職務怠慢以外の何物でもないと言えます。
心の中でこう叫ぼう!
「おまえの言葉が一番やる気を無くすんだよ。上司としての仕事をやる気あるのか?」
第1位 上司が部下に言ってはいけない言葉「だから言っただろう」
上司の完全な責任回避の言葉です。「オレは言ったよな、だから悪くないよな。おまえの責任だからな」と言う意味でしょうか。
同僚や後輩にそれはやめた方がいいとアドバイスした経験のある方は多くいると思います。その結果、同僚や後輩が失敗をしてしまい、悔しさ半分で「だから言っただろう」と言うことは良くあることです。
アドバイスというのは、本来強制力を持たないので、当然最後は行動した本人の責任であることで間違いではありません。
アドバイスした人にとっては、「せっかく言ってあげたのにな」と残念な気持ちになるとは思いますが、人は自分で失敗しないとわからないことや、自分で決めたことを実行することにより、失敗はしたが納得性を得る面もあります。
しかし、ここで言う「だから言っただろう」は、上司が部下に発した言葉です。上司が部下にすることは、アドバイスではなく指示命令です。
もし失敗する確率が高いことを知っていて、それは部下の経験を積ませることであったり、成長に繋げることであれば、このような発言にはなりません。
逆に、このことで気づいたことや学んだことをキチンと聞き出し、部下をさらに成長させる支援をすることでしょう。このような上司の下では安心して仕事ができますが、残念ながらそうでない上司も少なくないのです。
このダメ上司は、骨髄反射的にこの言葉を言ってしまいます。保身のかたまりのような人間なのです。世の中的に本当にどうしようも無い人間と言えます。しかし昭和は、このような人間をたくさん作り出してしまい今もあらゆる場所ではびこっているのです。
自分の職位を利用し、ただ部下のやったことに対してジャッジだけを行う。そのジャッジもかなり上司の主観にまみれていて、到底納得のできる内容ではない。こんな上司の元では全くやる気が起きないものです。
保身。人間のサガ。リーダーとしての敬意はこれを乗り越えたところから生まれる。尊敬される上司は、自分自身と戦っているのです。一瞬頭に浮かんだ「保身」を振り切り、私ができたことは何だったのかを考えるのです。
部下のやったことに対して、責任の取れない上司は、真のリーダーとは程遠い存在であると言えます。早くさよならしたいものです。
さよならできない人は、心の中でこう叫ぼう!
「わかっていたなら全力で止めろよ、おまえの言うことなんて信じないけどな」
まとめ
言葉一つで部下のモチベーションは大きく変化します。自分の言葉が相手にどのような影響を与え、それが会社全体でどのような生産性を生み出しているのか常に検証しましょう。真のリーダーとなり、尊敬される人になってください。